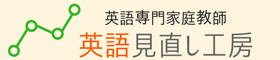高校リード問題集(リードA・B、英語Ⅰ)
英語家庭教師の高橋です。個人契約の家庭教師としてオンライン授業を東京の教室から全国に向けて展開しています。
『高校リード問題集』という、英文法の問題集の名前を聞いたことがありますか?
高校、塾・予備校、中高一貫校の中学でも、採用されている英文法のテキストで、
高校の教科書「論理表現」の文法問題を抽出した英文法専門教科書+問題集という感じです。
実際に、論理表現の教科書と併用している学校もあります。
塾や学校専売の為、一般の方は購入することができません。
私は出版元の「教育開発出版社」さんに「家庭教師を個人事業で行っている」とお話して、取引をしていただいています。
今回は、その高校リード問題集の使い方を中心にお話したいと思います。
高校リード問題集の種類
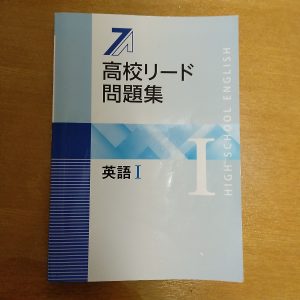
高校リード問題集にはいくつか種類がありますが、
英文法系に関して言うと下記のようになります。
- 英語Ⅰ
- 英語Ⅱ
- 英文法A
- 英文法B
私は、生徒の英語力に応じて『英語Ⅰ』・『英文法A』・『英文法B』の中から生徒に応じて組み合わて使用しています。
レベルや扱う範囲の大きさは、英語Ⅰ→英文法A→英文法Bです。
『英語Ⅰ』と『英文法A』は演習問題の難易度はそれほど変わらず、英文法Aの方が、扱っている文法事項範囲が広くなります。
例えば、英語Ⅰには「複合関係詞(whatever等)」や「受動態の分詞構文」などは含まれていません。
また『英語Ⅰ』は、英文解釈問題と言って短い文を和訳する問題が章末についています。
高校リード問題集の使い方
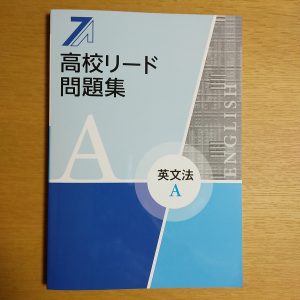
私の授業では、英文法の解説は自作のプリントで解説で行いますので、高校リード問題集の解説の参考程度に使います。
主に高校リード問題集は、解説した英文法の演習をやってもらい知識を定着させるために使っています。
同様に、学校や塾などの授業で使われているのであれば、
先生の解説をしっかり聞く→その文法事項(章)の問題を繰り返し解く
という流れで良いです。
一方で、自主課題として「自分で」解いて理解することを求められている場合は、やり方には注意してください。
高校リード問題集(英語Ⅰ、英文法A)であれば、各章の解説を読み、問題を解くという流れです。
注意点は、解説は章のすべてを一気に読むのではなく、章の中の小項目ごとに読み、その解説に対応した問題を解きます。
例えば「完了形」という文法事項であれば、「現在完了(小項目)」の解説のみを読み、現在完了の問題部分のみを解きます。
そして次の小項目である、「過去完了」の解説→「過去完了」の問題、という流れで進めます。
具体的には、
高校リード問題集英語Ⅰあれば
- 小項目の解説を読む(例文を訳しながら)
- 小項目ごとの「確認問題」を解く(「確認問題」がない小項目もあります)
- 「STEP1」のうち、その小項目に対応した問題を解く
- 章内のすべての小項目について1~3が終わったら「STEP2」を解きます
高校リード問題集英文法Aであれば
- 小項目の解説を読む(例文を訳しながら)※見開きで右側のページ、「確認問題」があればそれも解く。
- 「STEP A」のうち、その小項目に対応した問題を解く※見開きで左側のページ
- 章内のすべての小項目について1~2が終わったら「STEP B」を解きます
※英文法Aには「確認問題」があまり多くありません。
高校リード問題集英文法Bについて
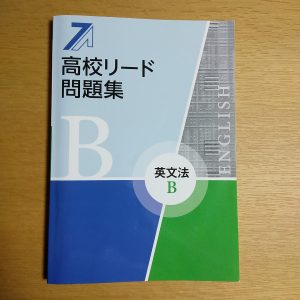
『高校リード問題集 英文法B』は、『英語Ⅰ』や『英文法A』と比べると基礎養成期の生徒さんには難しいと思います。
本格的な受験勉強を始めてやる生徒さんや、文法に自信のない生徒さんに「リードB」を最初の一冊としてやってもらうことは、ほとんどありません。
扱っている英文法項目は『英文法A』とは大きくは変わらないのですが、リードBの特に「STEP2」では大学受験問題が多くなり、単語レベルが難しくなります。
語彙力の少ない生徒さんが使用する場合は注意が必要です。
また、各文法項目内で扱う小項目が『リードA』よりも『リードB』のほうが多くなっています。
例えば、「完了形」では、「未来完了進行形」についてリードAでは「参考」として触れるだけで演習問題が無いのに対して、リードBでは演習問題も掲載されています。
高校リード問題集『英文法A』や『英語Ⅰ』とくらべて、解説部分も各文法事項内の「小項目」が多くなっています。例)補語になる関係代名詞that→リードA:無、リードB:有
自分で進める場合の使い方は、『英語Ⅰ』と同様です。
小項目の解説→演習(確認問題)→STEP1→小項目の解説・問題すべて終了後、STEP2
高校リード問題集との出会い
私が長年お世話になっていた予備校では「開講前特訓」として大学受験が終わった2月後半~4月の授業が始まるまで、生徒に自立学習を確立させための「自習授業」がありました。
やり方は、英語のレベルチェックを受けて、生徒はレベルに合った教材を渡され、自習室に籠ってその教材にとりくみます。
そして、分からなくなったら「質問コーナー」に来て待機している英語科講師に質問をする、という単純なものです。
しかし、その特訓で上手く自立学習力を身につけた生徒は、見違えるように英語に対する勉強の仕方が変わっていました。
当時、その予備校で初めてその様子を見たころは、生徒の変貌ぶりに驚いたものです。
その「開講前特訓」で使われていたテキストが『高校リード問題集』でした。
その時以来、独立して家庭教師をはじめてからも、ずっと高校リード問題集にはお世話になっています。
- 大学入試に必要な英文法項目の網羅している点、
- ちょうど良い量の演習問題
- 適度な量の解説
しっかりと取り組めば必ず生徒の力になるこの本は、今では私の授業には欠かせない「相棒」です。